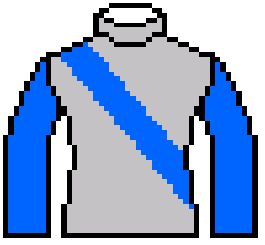ストーリー
サンデーサイレンスの系統が全盛となっている現代。だが昭和から平成初期にかけては、短距離血統と長距離血統の棲み分けが、いま以上に明確だった。
長距離血統種牡馬の代表格は、たとえばノーアテンション。馬場の重いフランスにおいて2400m以上で活躍したステイヤーだ。あるいはインターメゾ。セントレジャー勝ち馬であり、菊花賞・天皇賞(春)・有馬記念を制したグリーングラスの父であり、やはりスタミナ豊富な種牡馬である。
そして、ノーアテンションを父に、インターメゾを母の父に持つ馬として1985年に誕生したのがスーパークリーク。菊花賞を獲るための配合として、生産者・柏台牧場と、サラブレッドクラブ・ラフィアンの岡田繁幸氏が実践した配合である。
現代の価値観からすれば“重すぎる”ことになるのかも知れないが、スーパークリークは宿命へ向かって突き進んだ。
順調な歩みだったわけではない。
脚は外向していた。デビューは2歳12月まで遅れた。初戦は気の悪さを出して2着に敗れた。2戦目に勝ち上がったものの、以後は4着、3着。3歳3月・すみれ賞でやっと2勝目をあげるが、その後左前脚を骨折。春シーズンを棒に振ってしまうこととなる。
幸いにも秋には復帰できたが、神戸新聞杯は3着、京都新聞杯は6着と敗れ、菊花賞の優先出走権を確保することはできなかった。賞金順で見ても、フルゲート18頭に対してスーパークリークは19番目。生まれる前からの規定路線である菊花賞は、夢のまた夢に終わりそうな状況だった。
が、ここで僥倖がもたらされる。
岡田繁幸氏のラフィアン所属馬であるマイネルフリッセが、賞金上位であるにも関わらず菊花賞出走を回避。生みの親が示した粋な配慮によって、スーパークリークは無事に菊花賞のゲートに収まったのである。
そして1988年・第49回菊花賞は、スーパークリークの強さだけが際立つものとなった。
中団からスルスルと進出し、第4コーナーでは早くも先団に取り付いたスーパークリーク。直線では1完歩ごとに後続を突き放して5馬身差の圧勝だ。鞍上・武豊騎手が史上最年少クラシック制覇を果たしたのとともに、スーパークリーク自身も、宿命づけられた菊花賞Vを成し遂げたのである。
翌4歳シーズン、またも脚部不安に見舞われて順調に使えなかったスーパークリークだったが、秋には復帰して京都大賞典をレコード勝ち、天皇賞(秋)も制してスピード能力の高さも示した。さらに5歳春には、前年の覇者イナリワンを降して天皇賞(春)も勝利、天皇賞秋春連覇の偉業も達成する。
先祖から受け継いだ豊富なスタミナ、その能力に裏づけられたスピードの持続力で、相手をねじ伏せる。そんなレースぶりが印象的な競走馬であった。