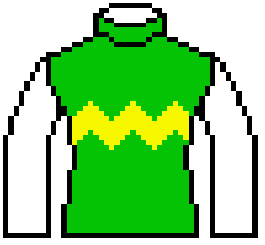ストーリー
名馬とは、数々の逸話に彩られ、逸話とともに生きる存在であるようだ。
皐月賞、宝塚記念、有馬記念などを制して天馬と呼ばれたトウショウボーイと、レコードタイムで毎日王冠を勝ったシービークインは、同じレースでデビューしたという因縁を持っていた。両馬引退後の1980年、この2頭の間には、漆黒の、ビロードのような肌を持つ子馬が誕生する。
ミスターシービーである。
シービーとは、生まれ故郷である千明(ちぎら)牧場の頭文字。馬名にこめられた期待の大きさがわかる。実はこのミスターシービー以前、1930年代にも初代「ミスターシービー」は走っていたのだが、大レースを勝利することなくターフを去っている。
夢は、2代目へ。血統の良さと美しさゆえ、早くから注目を浴びたミスターシービーは、出遅れグセを見せながらも怒涛の追込みを武器に1983年のクラシックを戦っていく。
デビューから9戦連続で1番人気に支持されることになるミスターシービー。出遅れて、後方を進んで、最終コーナーから直線にかけて不器用に順位を上げていくその姿は、誰からも愛されるものだった。
皐月賞では不良馬場を蹴り上げて自慢の末脚を炸裂させた。
日本ダービーではまたも出遅れたが、最終コーナーでは外の馬を弾き飛ばすようなマクリを披露、直線半ばで先頭に立つと、そこから堂々と押し切ってみせた。
そして秋、「ゆっくり上り、ゆっくり下れ」といわれる京都の坂を一気に駆け抜けて、菊花賞は圧巻の1着ゴールを果たした。
スタートでの立ち遅れが響いた3戦目・ひいらぎ賞の2着、久々だった秋初戦・京都新聞杯4着といった取りこぼしはあったものの、9戦7勝の鮮やかな成績を残して、ミスターシービーは、シンザン以来19年ぶりとなるクラシック三冠の大偉業を成し遂げたのだった。
古馬となった1984年、ミスターシービーには、1つの僥倖と、大きな壁が待っていた。
まずはグレード制の導入と距離体系の整備。中央競馬のレースに格付けがおこなわれ、各レースの施行距離も見直されることになった。それまで春秋とも3200mでおこなわれていた天皇賞も、秋のみ2000mへと距離が短縮された。この新生・天皇賞を直線一気のレコードタイムで制したのがミスターシービーだ。三冠のみならず「GI・2000mの天皇賞」の初代チャンピオンとしても名前を残すことになったわけだ。
が、時代はすでに1歳下の三冠馬、皇帝と称えられるシンボリルドルフの天下。ミスターシービーはジャパンC、有馬記念、翌1985年の天皇賞・春と三度シンボリルドルフと対峙したが、一度も先着することなくターフを去ることとなった。
かように名馬は、数々の伝説に彩られ、伝説とともに生きるものなのである。